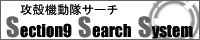梅に鶯、竹に虎
梅に鶯
紅葉に鹿
牡丹に唐獅子
竹に虎
輝く水を湛えた田園の中をくねる一本の道。そこを、一人の女が歩いていた。
杖のように左手に持った短槍の石突が、湿った土を抉ってはさく、さくと規則正しい音を鳴らしている。
「ただいま。」
立ち止まって背中の荷を背負い直しながら女が声を掛けた。まだ少女から抜け出したばかりの、若い女。
年の頃は数えで18に見えるが、何処と無く華やかさに欠ける、青いばかりの竹を思わせる雰囲気を纏っていた。
「お帰り、バルサ。」
声に振り返った青年が応えた。浅黒い肌に、慈しみを湛えた笑みを浮かばせている。
バルサと呼ばれた女は、それにつられるように少しばかり口元を緩めた。
「あれ?ジグロは?」
青年が立ち上がりながら尋ねる。
「用があるから先に帰ってくれってさ。タンダ、あんた膝に泥が付いてるよ。」
「え?ああ、ほんとだ。」
慌てて膝を叩くと、パラパラと半分乾燥した泥が落ちていく。
「なにをそんなに真剣に見てたのさ?子供みたいに膝泥だらけにして。」
「うるさいよ。ほら、これだよ。」
「ん?」
タンダが指差した先には、小さい桃色の花が咲いていた。
「花?」
「ああ、この花は普通黄色か白の花しか咲かせないんだ。珍しいからつい見入っちゃって。」
「あんたらしいね。」
くすっと笑みをこぼす。と同時に軽く眉を顰めた。
「!バルサ!」
「な、何?」
いきなり声を荒げて自分を呼ぶタンダに、バルサはたじろぐ。
「何じゃない。お前、怪我してるだろう?!」
「よ、良くわかったね・・・。」
「どっちだ・・・右手だな。」
言うが早いが、タンダはバルサの右手を取る。するりとマントが腕を滑り落ちた。
血の滲んだ粗末な包帯が露わになる。
「まったく、どうしてそうお前は無茶ばかりするんだ・・・。」
「そんなに心配しなくても、もう傷は塞がってるよ。」
「そういう問題じゃない!ほら、早く帰るぞ。ちゃんと手当てしなくちゃ。」
薬草で一杯になった籠を背負うと、タンダはバルサの先に立って歩き始めた。
零れ射す光の中を、二人は歩く。雪が溶けて久しい森の中は、来る夏へ向けて緑の色を強くしている。
程よく湿気を孕んだ風が、乾いた肌に心地良い。
ヨゴの春は気持ちが良いと、バルサは常々思っていた。乾燥した冷たい風が強く吹く山岳地帯から戻ってみると、その思いも一入になる。
空を見上げれば葉のあちこちに覗ける青く高い空に、白く雲が鮮やかに流れていく。
鼻腔を過ぎる空気は、強く薫って肺を満たす。
ふと前を見ると、タンダがちらちらとバルサを振り返っていた。
「タンダ?そんなによそ見してると躓くよ。」
「え?あ、ああ、そうだな・・・。」
前に向き直ったタンダが、不意に口を開いた。
「な、なあバルサ。」
「何?」
「バルサは、・・・いや、何でもない。」
「?」
バルサはいぶかしむが、前を歩くタンダの顔は見えない。
やがて森を抜け、開けた場所に出た。
「あれ?師匠。」
森を抜けてすぐ横の岩に座っていたのは、一人の小さな老婆であった。タンダの声に顔を上げると、岩を降りて仁王立ちになる。
「お出かけですか?トロガイ師。」
「ああ。まったく、いつまでもお前が戻らんから出発が延びちまったわ。」
バルサの問いに答えながら、持っていた杖でびっ、とタンダを指す。
「それ俺の所為ですか?朝はずっとゴロゴロしてたじゃないですか。」
「まったく減らず口の弟子にも困ったもんじゃ。」
「はいはい。で、お帰りはいつ頃に?」
「判らん。夏が終わるまでには戻ってくるが。」
「トロガイ師、何処まで行かれるのです?」
「さあな。ま、北の方をうろうろしてくるさ。」
タンダとバルサが来た道を歩き出すトロガイ。
「ああ、バルサ。」
数歩進んだ所で突然立ち止まり、振り返りながら言う。
「風呂はタンダに沸かしてもらえよ。」
「ええっ!俺ですか?!」
「トロガイ師、私は別に水浴びでも・・・。」
「師匠を待たせた罰だ。いいからしっかり旅の垢を落としておきな。」
それだけ言うと、二人の応えも待たずにトロガイはずんずんと去っていった。
タンダとバルサ、トロガイ、ジグロの四人が住まう小屋の、その影に置かれた大きな桶には、タンダの沸かした湯が並々と張られていた。
温めの湯に肩までつかり、髪の毛から耳の中までしっかりと濯ぐ。乾燥した風に当たり続けたバルサの体からは、湯が濁る程に砂埃が出てくる。桶の底に足の
裏を滑らせれば、ざりざりと音がした。
「バルサー、お湯足りてるかー?」
「充分だよ。熱さも丁度良い。」
ゆっくりと右の二の腕に湯を掛ける。傷口は塞がりはしたものの、まだ若干の痛みを伴う。加えて昨日の晩から熱を帯び始めていた。
左手をそっと傷口に重ねる。どくんどくんと波打つ熱さ。
「膿み始めたか・・・。」
護衛の仕事をしている間は必要最低限の手当てしか出来ない。しかもその痛みを襲ってくる輩にも、ましてや護衛している相手にも知られる訳にはいかなかっ
た。仕事に差障る程の怪我をするような用心棒は、客の信頼を落としかねないからだ。幼い頃からジグロのそうした背中を見て育ったバルサは、直感的にそれを
悟っていた。最も、ジグロの操る短槍を前にジグロに刃を届かせた者の数も、そうはいなかったが。
湯から上がって小屋に入ると、タンダが手当ての準備をしていた。目の前に座るバルサ。
「ああ、こりゃ完全に膿み始めてる。早い内に膿を出した方が良い。」
傷口を一目見たタンダはそう呟き、手馴れた様子で小刀を蝋燭の火で炙る。
「行くぞ。」
タンダの言葉に反射的に傷口から目を逸らし俯く。
じゅう、と音がする。遅れて、痛みがバルサを襲った。
下唇を噛んで耐える。
鉄の味が鼻腔を衝く。
空気が、焦げ臭い。
やがて刺すような痛みはゆっくりと消え、代わりにひんやりとした感触が傷口を撫でていった。
見ればタンダが薬を塗っている。
「さてこれで後は布を当てて包帯をすれば・・・」
タンダの口が不意に止まる。
「タンダ?」
バルサの顔をじっと覗き込むタンダと、目が合った。
「どうか・・・」
「ああ、やっぱりだ。」
「?」
タンダの指がバルサの口に伸びる。
「バルサ、唇切ってるぞ。」
「・・・え?」
「最初は紅でも注してるのかと思ったんだが・・・。」
言われて下唇を舐めてみれば、鉄の味がする事に気が付いた。
「本当だ。いつの間に・・・。」
「きっと山越えで唇が乾いてたんだろう。後で薬を用意しておくよ。」
「あ、有難う。」
「紅、か・・・。」
短槍の手入れをしながらバルサは先刻のタンダの台詞がずっと気に掛かっていた。
普段なら気にも留めないその言葉を、しかしバルサは幾度も思い出してはその度に溜息を吐く。
バルサは紅を注した事がない。
追われている身という境遇がそうさせたのか、或いは周囲にいる女性がトロガイのみであるという生活が理由なのか。
とにかく早くジグロのように強くなりたい一心で、気付けばそうした事に興味すら抱かずにきていた。
しかしその事に後悔しているかと言われれば、特にそういった感情は湧いてこなかった。むしろ、何を今更気にしているのかと自問したい位だった。
なのに、気になる。
ふう、と何度目とも知れぬ溜息が零れた。
その時、小屋の外にいたタンダの声が聞こえた。
「お帰りなさい、ジグロ。」
タンダのその声にバルサは短槍の手入れをしていた手を止める。振り返ると小屋の入り口に茜空を背負って立つ男の影が目に入った。
「お帰りジグロ。もう用事は済んだの?」
「ああ。」
言葉少なに答えたジグロは、短槍を入り口の所に立て掛け、背負った荷を降ろす。
「バルサ、傷の手当てはしてもらったか。」
「何だよジグロまで。もう済んだよ。」
「そうか。じゃあ右手を出してみろ。」
二の腕の包帯を見せるように右手をジグロに差し出すバルサ。
「そうじゃない。」
笑いながらジグロはバルサの掌を上向かせる。
ジグロの左手からバルサの右手に渡されたもの。
「貝・・・?」
「紅だ。さっき街で買ってきた。」
それは小さな二枚貝を容器にした紅だった。貝を開くと目に鮮やかな薄桃色が飛び込んでくる。
それを見た瞬間、バルサはやっと思い至った。
自分があれだけタンダの言葉を気にしていた理由。
今回の護衛相手には丁度バルサと同い年の娘がいた。花の様に笑い、たおやかにしかし凛として旅をこなしていた。
その娘が紅を注している様を見て、バルサは思わずその娘と自分とを置き換えていた。
もし、自分が、何事もなく生まれ故郷で父と暮らしていたら。
父は、私に紅を買ってくれて、私はそれをつけて女の衣服に身を包んでいたんだろうか。
仮定に過ぎない事は分かっていても、幻想に過ぎないと理解していても。それでも、その夢想は留まる事無くバルサの中から溢れ出していった。
そうして、己の両手を見て、改めてその夢を諦めるのだ。
幼い頃から短槍を握り続けた手。肉刺が出来ては潰れてを繰り返し、いつしか硬い皮膚に覆われていった掌。
傷だらけの腕。傷だらけの背中。身体。
その節くれ立った己の手の中に、あの娘の手の中にあった紅がある。
とうに花である事を諦めた、自分の手に。
「何でまた、急に・・・。」
「お前も年を越せば19だ。そろそろそういったものも必要だろう。」
そう言いながらジグロは武骨な手をバルサの頭に乗せた。
「ジグロ。」
「何だ。」
「有難う。でも・・・。」
紅を握り締めながらバルサは笑う。
「店の前であんたが紅を選んでるのを想像すると、笑えてくるよ。」
*
「バルサ。」
「ん?なんだいチャグム。」
「バルサの持っているその貝殻は何だ?」
バルサが紅を付け終わるのをじっと見守っていたチャグムが尋ねた。
「え、ああこれか。これは紅を入れる貝殻さ。」
「紅・・・?」
「ああ、女の人が唇に塗るんだ。二の后も持ってなかったかい?最も、宮のお方はもっと小洒落た物に入れているのかもしれないが。」
「そう言われれば持っていた気がする。」
「だろう?」
バルサは貝をそっと閉じる。
18の春、ジグロに貰った紅。
その紅はもうとっくに使い切ってしまったが、この貝殻だけは以前のままだ。
「全く、いい年してまだ捨てられないとはね・・・。」
「そんな事はない。バルサ。」
バルサの独り言を貝殻でなく紅の事だと勘違いしたチャグムが言う。
「バルサが紅を注す時の横顔は、とっても綺麗だ。花みたいに。」
了
神は世界を吟遊する。