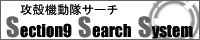異邦人は蝶の夢を見る
昔者、荘周夢為胡蝶。
栩栩然胡蝶也。
自喩適志与。
不知周也。
俄然覚、則遽遽然周也。
不知周之夢為胡蝶与、胡蝶之夢為周与。
周与胡蝶、則必有分矣。
謂此物化。
それはまるで夢のよう。
*
「それにしてもよー」
ふと一人が話題を振った。ランドセルを窮屈そうに背負い、刈り上げた頭の後ろで手を組んで見るからにガキ大将の風情。
「やっぱ蘭ねーちゃんのメシはうまいよな」
「そうですね。毎日あんなおいしいごはんを食べているコナン君がうらやましいですよ」
応えたのはひょろりと細長い少年。頬に散らばるそばかすが、愛嬌を持って微笑んでくる。学士帽と白衣を着せたらいかにもな学者といった趣。
「俺なんかいつもより食べ過ぎてゆうべずっと腹が痛かったんだぜ」
「だって元太君たらごはん6杯もおかわりするんだもの」
おかっぱを揺らしてくすくす笑うのは可愛い女の子。
「しかも全部大盛りで」
「しょーがねーだろ。すっげーうまかったんだからよ。なあコナン」
「あん?」
呼びかけられた眼鏡の少年はまだ本調子でないのか焦点の定まらない目をガキ大将へと向ける。
「おまえまた風邪ひけよ」
「どうしてそうなるんだよ…。まだこの風邪も治ってないってのに」
「そーすればまたお見舞いに行ってやるぞ」
「元太君の場合、目的はお見舞いじゃなくて蘭さんの作るごはんですけどね」
湧き上がる笑い声は、とても心地よく。
「じゃーなコナン!」
「早く風邪治るといいね!」
「蘭さんに昨日はごちそうさまでしたって伝えておいてください!」
三者三様の言葉を送り、彼らは去っていく。
彼と2人きりになったところで、私は早速尋ねた。
「で?」
「ん?」
「どんな悪夢を観てたのかしら?」
先日、彼が私の作った解毒薬で 「工藤新一」に戻った途端に高熱で倒れ魘されていた時の事を訊いた。
「ああ、あの時か。いやまあ確かにあれは悪夢と言えなくもねぇな…」
普段より若干掠れた声でつぶやく。
「無事に高校生の姿に戻れたんで学校に行ってみたら何かおかしいんだ。下駄箱に上履きが無かったり、教室に行っても知ってる奴が一人もいなかったり。蘭も見つからない。けど、オメーらがいるんだ。元太と、光彦と、歩美と、灰原が」
「…」
「みんな帝丹高校の制服着てな。『探偵クラブ』なんて部活作ってよ、当然のように俺を呼ぶんだぜ。『コナン』って」
カタン、カタン、固い音が背中から聞こえる。
「夢の中のオメーから事情を聞いて『江戸川コナン』のまま高校生になったって聞いた時にはそれこそこの世の終わりに思えたな」
「あら、私はむしろいい夢だと思うけど」
カタン、カタン、カタン。もう聞き慣れてしまった音。
「はあ? 何でだよ。元に戻れないまま10年だぜ? 悪夢に決まってんじゃ…」
「10年、組織の追手から逃れ続けられたとしたら」
「?」
立ち止まる足音。背中の音は、聞こえない。
「一生逃げ切れる可能性は、高くなるわ」
「そんな訳…」
「裏の世界って表より早く時間が経つものなのよ。10年経ったら忘れられていてもおかしくないわ」
「…灰原、オメー、本気で言ってんのか?」
「冗談で話せる内容だと思う?」
重たい沈黙。河川敷を流れる赤い風は、冷たい。
「…元に、戻りたくないのかよ」
彼の顔を振り向く。自分がどんな顔をしているかは、わからない。眼鏡の反射した彼の顔も、わからない。
「さあ、どうかしら」
川の反射に目を細める。
「少なくとも元に戻ったところで、私の家族はもういないし、会いたいと思える友達もいないわ。でも…」
「今なら、仲間が、友達がいるってか…?」
かさかさにひび割れた声は、きっと風邪の所為だけじゃない。
「貴方にとって今の生活は仮のモノなんでしょうけど、でも、彼らにとっては『江戸川コナン』という存在は真実なのよ。あの子達だけじゃない、小林先生や蘭さんだって同じ。『工藤新一』という存在が真実であるのと同じくらいに、彼らにとって既に『江戸川コナン』はニセモノじゃないのよ」
くるり、前を向き再び歩き出す。カタン、カタン、カタン、教科書がランドセルの中で揺れる。
「勿論『灰原哀』という存在も、ね。むしろ彼らにとっては『宮野志保』という存在の方がニセモノだと言えるかも知れないわね」
「灰原…」
後ろで立ち止まったままの彼はそれ以上何も言えない。言えない事を知っていて私は言う。
カタン、カタン、カタン。虚しく響く音に追い立てられながら、私は慣れた道を歩く。
「ただいま」
家に帰ると博士はいなかった。机の上の書置きを確認する。大丈夫、買い物に行ってるだけ。
以前博士が何も言わずに出かけた時、組織の人間に攫われたか或いは殺されたかと一日中強迫観念に囚われていた事を気に病んで、それ以来外出の際には必ず書置きを残してくれるようになった。
書置きの紙をそのままにセピア色のランドセルをソファに落とし、私は研究室の扉を開けた。
過去の記憶を捨てるつもりはない。
家族との思い出、研究で得た罪、それらが全て私を作ったのだから。
けれど、こうして小学生としてのそれなりに平凡な生活を繰り返す中で、思う。
実は今までの記憶は単なる夢で、私はただの女の子なのではないか、と。
家族に先立たれる不幸はあったけれど、親切な養父に恵まれ楽しい仲間もでき、名前で呼んでくれる友達も得た。
ひょっとしてこれは夢なのではと疑う事もなく、ただ平凡に、幸福に生きる。
それはまるで蝶の見る夢のように。
ふう、溜息を吐くともう窓の外は真っ暗だった。
博士はまだ帰ってきていない。
沸き起こる不安を理性で打ち消そうと足掻く。
その時、呼び鈴が鳴った。
どくん、鼓動が高くなる。
最悪の事態が頭を過る。
玄関のドア一枚の先に誰がいるのか。
恐怖で椅子から立ち上がれない。
誰?誰なの?
「おい灰原、いるか?」
ドアの外から掛けられた声は、若干擦れていたけれど私の耳にちゃんと届いて私を安心させた。
動悸を抑えつつ白衣のまま研究用の部屋から出ると玄関の扉を開けた。
「全く…まだ喉が痛いんだから何回も大声出させるなよ…」
マスクを顎までずり下ろした少年が、そこにいた。
「あら、そんな風邪も治りかけの人間がこんな時間に何の用?」
努めて冷静に返す。
「ほら、これ」
少年が差し出したのは小さな箱だった。
「これ…」
箱には小さく上品にプリントされた特徴的なブランドロゴ。
「オメーこのブランド好きだったよな?」
化粧箱を開け、中のケースの蓋を開くと、イチョウの葉をあしらった金色のピアスがきらきらと輝いている。
それはフサエ・ブランドのピアスだった。
「どうしたのかしら、急にこんな物を持ってきて」
「おっちゃんの依頼者がお礼に送ってくれたものを貰ってきたんだよ」
「で、これを私にくれるって訳?」
「元の身体に戻ったら、それを付けろよ」
「私にも元に戻る為の目的を見つけろって言うの?残念だけど、そんな理由だけで努力する気は…」
「また友達になればいいだろ」
私の言を遮って彼は言う。
「元の身体に戻ったら、またあいつらに仲間になってもらえばいいだろ。また一緒に遊べばいい。今はまだ歳が離れすぎているように思えるかもしれねーけど、でも元に戻って10年20年経てば歳の差なんて気にならなくなる。それまでずっと友達でい続ければ良いじゃねーか」
「そんな事…」
出来るわけない、と言いかけて私は黙った。
「出来るさ。全部理由を話せばあいつらだって分かってくれる。また仲間に誘ってくれるさ。だから『宮野志保』がニセモノだなんて言うなよ。今は『灰原哀』だけが存在しているってだけで、元の身体に戻れば『宮野志保』だって『灰原哀』だってホンモノになるんだからよ」
私の手の中で輝く金色が、一瞬滲んだような気がした。
ふ、と目を閉じる。目を開けると得意気な少年の顔がそこにあった。
「全く、こんな事の為にわざわざ食事も摂らずにここまで来るなんてね」
「え…なんで分かるんだ?」
「お腹、鳴ってるわよ」
「げ、マジで?!」
「冗談」
「テメ…」
いつものように彼をからかっていると博士が帰ってきた。
「あら博士、お帰りなさい」
「なんじゃ新一、ワシに用でもあるのかね?」
「いや、博士に用はないけど…って博士、また買い物の途中で3丁目の古道具屋に寄り道してきたな?」
「なっ、何で分かるんじゃ?!」
「博士から葉巻の匂いがプンプンするんだよ。この匂いの葉巻を愛飲している博士の知り合いっていったら古道具屋の店主しかいねーからな」
「言われてみれば確かに…」
博士が自分のジャケットの匂いを嗅ぐ。確かに博士が動く度に甘い匂いがふわりと漂っていた。
「で、工藤君も晩御飯食べてくの?」
「なんじゃ、まだ食べておらんのか」
「今から帰ったんじゃあ食べるの晩くなりそうだし…食べてくよ」
「今日は哀君が食事当番じゃったかの」
「げ。やっぱり帰りま…」
「ダメよ。食べてきなさい」
「ハイ…」
小さな箱をポケットにしまい、博士の荷物を受け取り台所へと向かう。
歪に膨らんだ白衣のポケットは、思ったよりも心地のいいものだった。
了
降る降る夢と世界のまにまに。